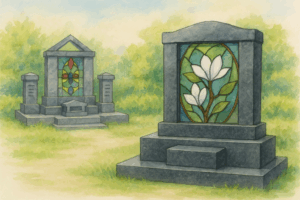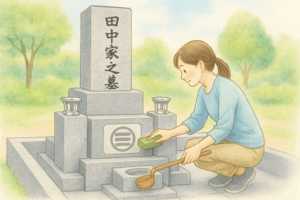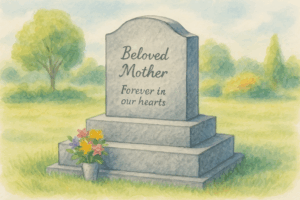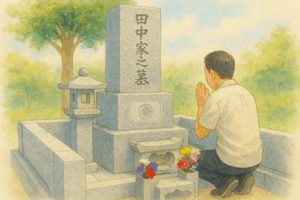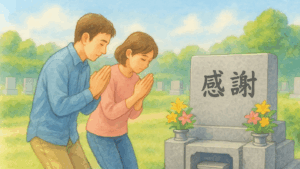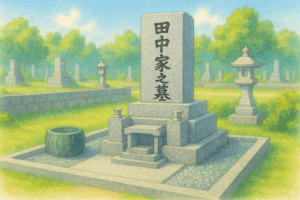墓石選びで迷うポイントのひとつが「石の種類」です。
石材によって色味、風合い、耐久性、価格などが大きく異なり、後悔しないためには基本知識が欠かせません。
本記事では、日本や海外で使われる墓石用の代表的な石の種類と特徴をわかりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリット、選び方のコツまで詳しく紹介します。
墓石に使われる主な石の種類
墓石は大きく分けて「花崗岩(御影石)」「安山岩」「閃緑岩」などの火成岩が中心です。
天然石の中でも硬度と耐久性の高い石材が選ばれており、それぞれに風合いの違いや長所・短所があります。石の種類によって、価格帯だけでなく、加工のしやすさ、艶の出方、経年変化の具合も異なります。
「見た目が気に入った」という理由だけで選ぶと、数十年後に後悔することも。以下で石材ごとの特徴を詳しく見ていきましょう。
花崗岩(御影石)
墓石の代表格ともいえる石材で、全国で最も多く使用されています。
- 高硬度で吸水率が低い
- 色や模様のバリエーションが豊富
- 艶出し加工に向いており、高級感が出やすい
たとえば、香川県の庵治石は「日本一の銘石」とも称され、キラキラした模様(斑)が特徴です。細粒で斑が浮かび上がる見た目は、唯一無二の高級感を放ちます。
大島石(愛媛)も風化しにくく、全国の寺院墓地や公営霊園で広く採用されています。特に中目や細目は見た目のバランスが良く、価格と品質のバランスに優れています。
海外産では、インドのクンナムが漆黒の艶と高耐久性で人気。墓石展示場でも一番目立つ位置に置かれることが多い石種です。黒が濃く、艶持ちも良好で、「格式を感じさせる墓石にしたい」というニーズに応えます。
安山岩
日本の墓地で古くから親しまれてきた、比較的柔らかめの火成岩です。
- 素朴で温かみのある風合い
- 吸水率はやや高く、経年劣化しやすい
- 加工はしやすいが艶出しには向かない
代表的なのが茨城県の真壁石。ザラっとした質感が特徴で、昔ながらの和型墓石に多く使われます。表面が滑りにくいため、石塔だけでなく階段や敷石にも活用されます。
「故人の人柄を素朴に表したい」「控えめで落ち着いた雰囲気を大切にしたい」という場合に選ばれることが多い石です。
閃緑岩
硬く重厚な石質で、高級墓石や社寺建築などに用いられます。
- 黒っぽい色味で重厚感がある
- 非常に硬く、耐久性が高い
- 加工は難しいが、長寿命
福島の浮金石や山梨の山崎石、また岡山県産の備中青みかげ(矢掛石)などは、重厚な風格や独特の風合いを求める方におすすめです。光沢よりも落ち着きと力強さを重視したい方には最適な選択肢です。
たとえば、浮金石は微細な黒粒が入り混じり、控えめな光沢をもつ質感が特徴。「いかにも新しい墓石」といった印象を避け、落ち着いた雰囲気に仕上げたい方には向いています。
加工が難しいため、施工には熟練した職人の技術が必要で、施工店選びも重要になります。
輸入石材(中国・インド・南アフリカなど)
コストパフォーマンスに優れた輸入石も多数使われています。
- 黒やグレー系を中心に種類が豊富
- 国産より低価格な傾向
- 品質の差が大きいため選定に注意が必要
インドのアーバングレーや中国のYKDは、国産に比べて3割以上安い場合も。品質が安定していればお得ですが、石の質感やランク差があるため、必ず現物確認をしましょう。
特に安価な石材は、吸水率が高かったり、色ムラがある場合があるので注意が必要です。「この価格で本当に大丈夫?」という視点も大切です。
一方で、南アフリカ産のインパラブラックなどは、品質・耐久性・色艶に優れており、国産高級石と肩を並べる評価を受けています。選ぶ際は、単なる価格比較ではなく、石材の証明書や実績を確認しましょう。
次項では、石種による見た目や耐久性の違いをさらに深掘りしていきます。
石種ごとの見た目・風合いの違い
墓石は見た目で印象が大きく左右されるため、石種ごとの色・模様・艶感を把握することが大切です。
同じ花崗岩でも、粒子の細かさや模様の出方によって「高級感がある」「柔らかく穏やか」といった印象が変わります。
色合いの違いと印象
| 色系統 | 主な印象 | 使用される石種例 |
|---|---|---|
| 黒系 | 格式・重厚感 | クンナム、インパラブラック |
| グレー系 | 落ち着き・調和 | 大島石、アーバングレー |
| 白系 | 清潔感・明るさ | 稲田石、G603(中国) |
| ピンク系 | 優しさ・個性 | 万成石、ピンクローズ |
| 青・緑系 | 自然・静けさ | 庵治石、アズーロ |
同じ黒系でも、インド産のクンナムは艶やかで重厚、国産の浮金石は落ち着きのある鈍色と、選ぶ石で雰囲気が変わります。
「静かで控えめに」「華やかさを演出したい」など、希望する印象に合った色味を選びましょう。
粒子の細かさと表面の仕上がり
- 細粒:艶が出やすく、上品な見た目に(例:庵治石)
- 中粒:標準的な仕上がりで、安定感がある(例:大島石)
- 粗粒:個性が強く、模様が浮き出やすい(例:万成石)
特に庵治石のように、斑(ふ)と呼ばれる粒模様が細かく入り交じる石は、唯一無二の風合いとして高く評価されます。
耐久性と吸水率による違い
墓石は屋外に長年設置されるため、「耐久性」と「吸水率の低さ」は非常に重要です。
耐久性が高ければ風化やヒビ割れに強く、吸水率が低ければ苔や汚れが付きにくくなります。
吸水率の目安
| 石種 | 吸水率の目安 | 耐久性の特徴 |
|---|---|---|
| 庵治石 | 0.05%以下 | 変色・風化に非常に強い |
| 大島石 | 0.08%程度 | 全国的に安定した人気 |
| クンナム | 0.03%程度 | 水をほとんど吸わない |
| YKD | 0.15%以上 | 若干の水シミリスクあり |
目に見える部分だけでなく、内部からの劣化を防ぐためにも吸水率は要チェック。
「見た目は似ていても、長年使った後に違いが出る」ことを理解し、後悔しない選択を意識しましょう。
メンテナンスのしやすさ
- 黒石は水垢が目立ちやすいが艶が長持ち
- 白石は汚れがつきやすく定期清掃が必要
- グレー系はバランス型で清掃の手間が少なめ
清掃頻度やメンテナンス方法によっても、長年の印象が変わります。
日頃の手入れに不安がある方は、グレー系の石を選ぶと手間を抑えつつ美観を保ちやすくなります。
まとめ
墓石の石種選びは「色」「耐久性」「風合い」「価格」など、さまざまな要素を総合的に見て判断する必要があります。
選択肢が多いほど悩むかもしれませんが、逆に言えば“理想のお墓に出会える”可能性も広がります。
ぜひ、実際の石を見て触れて、家族や石材店と相談しながら、ご自身の想いや故人の個性に合った石を見つけてください。
納得のいく石選びは、後悔のないお墓づくりへの第一歩です。